
「デジタル終活」とは?始め方やポイントを解説

賃貸物件の管理に携わる皆さん、もしも入居者さんがお亡くなりになったら…と想像したことはありますか?
超高齢社会の今、単身でお住まいの方の「孤独死」や「急逝」といったケースは残念ながら増え続けています。
そんな時、頭を抱えるのが、「残された荷物(残置物)をどうすればいいのか?」という問題でしょう。
相続人の方の連絡先が分からなかったり、連絡が取れなかったりすると、賃貸契約の解約がスムーズに進まず、次の入居者募集にも影響が出てしまいます。
「勝手に捨てていいの?」「費用は誰が負担するの?」「早く次の入居者を見つけたいのに…」
こんなお悩みをお持ちの賃貸オーナーさんや管理会社さんのために、国土交通省が「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(以下、「モデル契約条項」といいます。)を令和6年3月に策定しました。
これはまさに、賃貸管理の現場で起こりがちな「もしも」のトラブルを未然に防ぐための画期的な仕組みです。
このコラムでは、賃貸管理の担当者の皆さんが安心して業務を進められるよう、この「モデル契約条項」について、分かりやすく丁寧に解説します。
本資料では、高齢入居者受け入れの現状と課題、独自調査に基づいた賃貸管理会社938社の見守りサービス導入状況を解説します。
高齢入居者の受け入れに不安をお持ちの方には必見の資料となります。
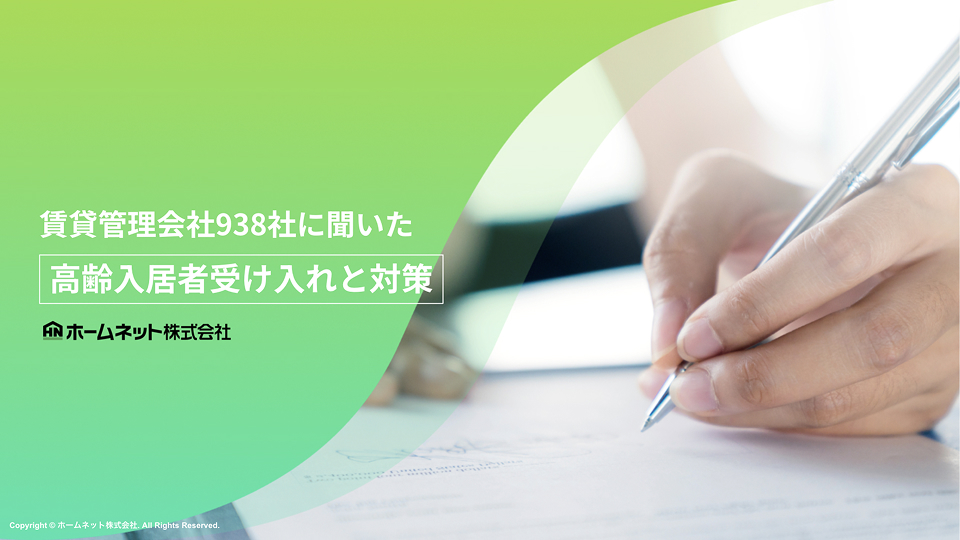
賃貸物件の「残置物」とは、賃貸借契約が終わったにも関わらず、物件の中に残されたままになっている家具、家電、衣類、日用品、ゴミなど、あらゆる物品を指します。
引っ越し時の置き忘れはもちろん、特に問題となるのが、入居者さんがお亡くなりになり、ご家族などと連絡が取れないケースです。
残置物が処理されないと、物件の引き渡しや次の入居者募集が遅れ、オーナーさんや管理会社さんにとって大きな負担となります。
国土交通省は、この残置物を巡る様々なリスクを「残置物リスク」と呼び、その対策として「モデル契約条項」を策定しました。
モデル契約条項は、単身の高齢者の方がお亡くなりになった際に、賃貸契約関係と残された荷物をスムーズに整理することを目的としています。
超高齢社会の日本において、賃貸物件で単身の方が亡くなるケースは増加傾向にあります。
これは、賃貸管理において避けられないリスクの一つです。
モデル契約条項は、賃貸経営のリスクヘッジとして非常に注目されています。
このモデル契約条項が必要とされる主な理由は以下の3点です。
超高齢社会が進む中で、身寄りのいない単身高齢者の賃貸入居は今後も増加が見込まれます。
物件によっては、こうした方々の入居を受け入れることで、空室対策にも繋がります。
その際に、モデル契約条項に基づいて契約を締結することには、以下の大きなメリットがあります。
「残置物の処理等に関するモデル契約条項」は、高齢化社会における賃貸管理の新たなスタンダードとなる可能性を秘めています。
家財整理や残置物処理といった、これまで賃貸管理の現場で課題となっていた問題に対応できるものとして、今後ますます注目が集まるでしょう。
賃貸管理のプロとして、こうしたリスクに対してどのような対策を講じるかは、賃貸経営の安定性にも直結します。
ホームネットでは、残置物対応の一環として「家財整理サービス」をご提供しています。
ご依頼内容に応じて、(一般社団法人)家財整理相談窓口の加盟事業者の中から、信頼できる業者をご紹介し、お見積もりの手配をいたします。
お見積もりは無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
ホームネットの家財整理サービスについて、詳しくは下記のリンクよりご覧いただけます。
最新記事
アーカイブ
INQUIRY