
「デジタル終活」とは?始め方やポイントを解説

日本では高齢化や単身世帯の増加、持ち家率の低下に伴い、住宅確保に困難を抱える人々が増え続けています。
しかし、孤独死や家賃滞納などのリスクから、大家が入居を敬遠するケースも少なくありません。
こうした課題を解決し、住宅確保要配慮者が安心して住まいを確保できる環境を整えるため、2024年3月に住宅セーフティネット法の改正案が閣議決定されました。
本コラムでは、法改正の背景と改正内容、不動産業界への影響について解説します。
本資料では、高齢入居者受け入れの現状と課題、独自調査に基づいた賃貸管理会社938社の見守りサービス導入状況を解説します。
高齢入居者の受け入れに不安をお持ちの方には必見の資料となります。
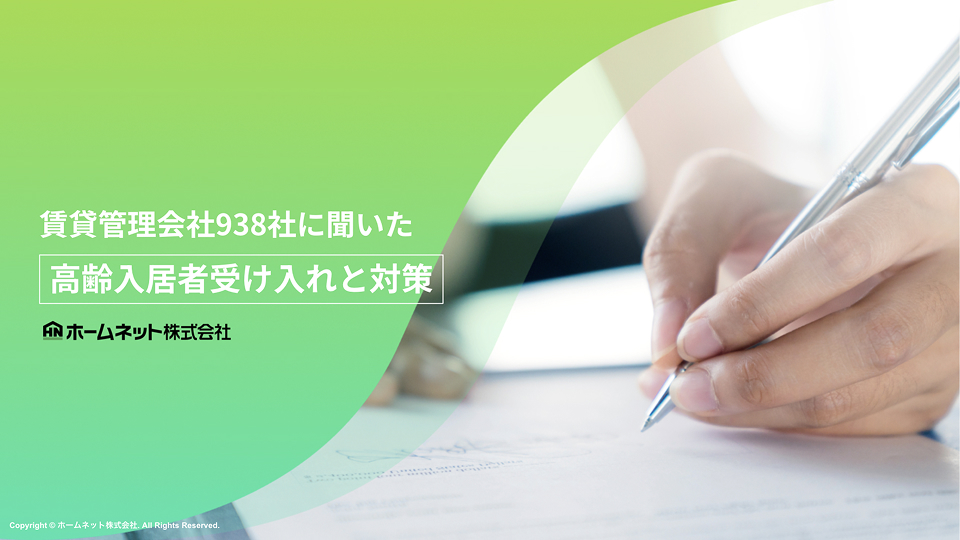
住宅セーフティネット法(正式名称:「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」)は2007年に施行されました。
この法律が制定された背景には、以下のような社会的課題がありました。
これらの背景をもとに制定された住宅セーフティネット制度は、以下3つの柱から成り立っています。
1.住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
大家が都道府県等に物件情報を登録し、都道府県等が住宅確保要配慮者へ情報提供をする制度。
2.登録住宅の改修・入居への経済的支援
登録住宅の改修への支援としては改修費に対する補助制度があり、登録住宅の入居者への経済的支援としては
家賃と家賃債務保証料の低廉化に対する補助がある。
3.住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援
不動産関係団体、居住支援団体、地方公共団体からなる居住支援協議会等が住宅確保要配慮者と物件のマッチ
ングや入居支援を行う。
・高齢者
・低所得者(生活保護受給者、非正規雇用者、収入が一定以下の世帯)
・障害者
・子育て世帯
・災害被災者
・そのほか国土交通省令で定める者
2024年3月8日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」等の一部を改正する法律案が閣議決定されました。
今後も、単身世帯の増加や持家率の低下等により、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズは高まることが見込まれています。
しかし、孤独死や死亡後の残置物処理等の課題への不安から、住宅確保要配慮者に対する拒否感を持つ大家は少なくありません。
住宅セーフティネット法の施行によって居住支援法人の数は着実に増加しているものの、支援体制には限界がありました。
そこで、住宅確保要配慮者が円滑に住まいを確保できる環境を整えるため、住宅政策と福祉政策が一体となった居住支援機能の強化が求められるようになりました。
先述の「ⅳ.”入居後の変化やトラブルに対応できる”住宅の創設」として居住支援法人等が大家と連携し、①日常の安否確認や見守り、②生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う住宅(居住サポート住宅)を創設しました。
現行法では、「大家が拒まないこと」、「物件情報を公開すること」によって住宅確保要配慮者へ住宅が提供されています。
改正法案では、これに「居住支援法人等がサポートを行うこと」が追加されました。
具体的には、ICT等による安否確認サービスや居住支援法人等の訪問等による見守りを行いつつ、生活や心身の状況が不安定になったときには福祉サービス(困窮者自立支援、介護等)へ連携します。
また、生活保護受給者が入居する場合は、住宅扶助費(家賃)の代理納付(受け取った住宅扶助費から支払うのではなく保護の実施機関が賃貸人に直接支払う方法)を原則化したり、先述「ⅲ.”家賃の滞納に困らない仕組み”の創設」の認定保証業者が家賃債務保証を引き受けることとしました。
住宅・福祉が一体となった居住支援体制の整備を推進するため、国土交通省と厚生労働省が共同して基本方針を策定するとともに、居住支援協議会の設置を促進します。
市区町村による居住支援協議会の設置を努力義務化し、住まいに関する相談窓口から入居前・入居中・退去時の支援まで、住宅と福祉の関係者が連携した地域における総合的・包括的な居住支援体制の設備を推進します。
国はこの改正法案の施行を2025年10月1日としており、それによって以下の目標達成を目指しています。
今回の法改正により、セーフティネット住宅の登録制度が拡充され、空室物件を有効活用する機会が広がります。
登録にあたってバリアフリー改修や設備改善が必要な場合には、改修費の補助制度が用意されているためリフォーム投資へのハードルが下がり、物件価値を向上させるチャンスにもなります。
また、居住支援法人との連携強化により入居後のサポート体制が整備されることで、大家や管理会社の負担が軽減されるとともに、新たな需要層の取り込みによる賃貸市場の拡大や競争の変化も見込まれます。
今回の改正は、住宅確保要配慮者の受け入れリスクを軽減する施策が多く盛り込まれており、大家にとっては検討しやすくなります。
また、安否確認サービスや居住支援法人による見守り、福祉サービスへの連携支援が充実することで、入居後のトラブルや不安の軽減が期待されています。
さらに、国や自治体による改修費補助や家賃債務保証制度の活用により、経済的な負担や家賃滞納リスクが抑えられ、物件価値の向上や空室対策にもつながります。
これらの施策により、住宅確保要配慮者が安定した住まいを確保しやすくなることが期待され、大家にとっても、新たな需要層を取り込むチャンスとなり、社会全体での居住支援体制の充実が一層促進されるでしょう。
改正のポイントの1つである「居住サポート住宅」における安否確認サービスや見守りに関して、ホームネットでは電球を使った「HNハローライト」という見守りサービスを提供しています。
サービスの詳細については、下記のリンクをご覧ください。
最新記事
アーカイブ
INQUIRY